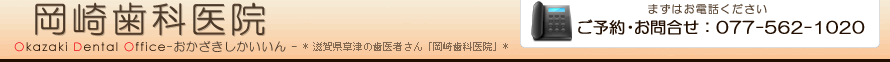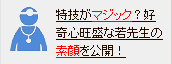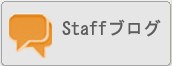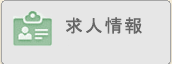インプラント・審美歯科・ホワイトニング・白い歯・スポーツ歯科・訪問・往診
■レントゲン撮影の安全性について 胎児への影響
■中国製の歯科技工物から検出された有害金属の問題について
■インプラントの使いまわしの問題について
レントゲン撮影の安全性について 胎児への影響
歯科診療において、レントゲンは、必要不可欠の道具です。
しかし、放射線を浴びること、つまり、『被曝』が伴います。
さて、被曝についてですが、『自然被曝』という言葉があります。それは、天然に存在する放射線源による被曝のことを言います。 わかりやすく言えば、『人間は、普通に生活しているだけで被曝している』ということです。
では、その自然被曝とは、どれくらいの放射線を浴びているのでしょうか。
被曝したときの放射線の量を、Sv(シーベルト)という単位で表しますが、世界の平均は、年間に2.4mSvといわれています。
当然、地域によりその数値は変わるのですが、日本では1.5 mSvと世界平均より低めです。
反対にブラジルやインドでは、10 mSvと、世界平均の4倍以上、日本の6倍以上になる地域もあります。
(ちなみに、東京ニューヨーク間を航空機で往復するだけで0.19mSvの放射線を浴びることになるそうです。なお、これらの数値は、国連放射線影響科学委員会報告に準拠しています)
この数値を覚えていておいてください。
さて、歯科のレントゲン撮影による被曝ですが、デンタルレントゲンという、口の中にマッチ箱サイズのフィルムを入れる撮影方法のもので、0.02 mSvほど、また、お口全体を撮影するパノラマレントゲンと呼ばれているもので、0.04 mSvほどです。 また、当院のレントゲンは、デジタル処理をしておりますので、普通のレントゲンと比較し、1/2から最大1/10に軽減されます。 ですから (遠慮して1/8くらいにしても)、デンタルレントゲンで、0.0025 mSv、パノラマレントゲンで0.005 mSvくらいになります。
つまり、歯科での一回のレントゲン撮影は、自然被曝の0.4パーセントを下回ることになります。
ちょっと変な計算をしてみましょう。
日本の年間自然被曝(1.5 mSv)は、世界平均(2.4 mSv)より0.9 mSv下回っています。
この0.9 mSvというのは、デンタルレントゲンが360枚、パノラマレントゲンが180枚に相当します。 一年間に歯医者でレントゲンを数百枚撮って、世界の平均的な自然被曝に到達する、という程度なのです。
こういう計算に意味があるかどうかわかりませんが、歯科のレントゲンがいかに微量であるかということをご理解いただければ幸いです。
胎児に影響が出る被曝量は、100 mSvといわれています。
100 mSvといえば、デンタルレントゲンが40000枚撮影分に相当します。
この数字より、胎児への影響がいかに少ないかはわかりますが、0でない以上、レントゲン撮影はできるだけひかえさせていただいています。
無意味なレントゲン撮影は許されません。
微量であれ無駄な被曝は避けるべきですが、それでもレントゲンを撮影するのは、患者様の病状を少しでも正確に診断するためですので、ご理解お願いします。
心配な方はおっしゃってください。撮影を控えさせていただきます。
(レントゲン写真がなければ処置が不可能な場合もあります。場合によっては処置を見送ることや、他の医療機関に紹介することもあるかと思いますがご了承のほどよろしくお願いします。)
中国製の歯科技工物から検出された有害金属の問題について
2010年の2月にTBS「報道特集NEXT」にて、中国製の技工物に有害金属が含まれているという内容の番組が放送されました。 そのためか、当院の患者様のみならず、私の友達の友達という人までもが歯科の金属について多くの質問をいただきました。
日本の技工所では、厚生労働省が認可をして、規格化された金属しか使うことができません。
中国の技工所では、その規格というのは適応されないので、日本で使用が認められていない、非常に有害な金属、場合によっては発がん性がある金属までもが使われる可能性があります。自分の口のなかのことですから、心配にならざるをえませんね。
結論から申しますと、日本の歯科医師が中国に技工物を発注するってことはごく稀だと思われます。
私の周りで、中国に技工物を依頼している先生はいません。ただ、我々が日本の技工所に発注しても、その技工所が、下請けで中国の技工所に出している可能性があります。
そこで、いくつかの技工所に聞いてみました。
皆様がいうには、“金属の成分が心配なので、うちではしておりません”とのことでした。
中国製だから問題あるか、といえばそうではなく、また、日本製なら絶対に問題ないか、といったらそれを証明はできません。技工士の先生方は、我々歯科医師のパートナーになるわけですから、技工の内容について相談ができる間柄で、信頼できる技工士の先生にしか発注しておりません。
当院の歯科医師、岡崎全宏は、現在、歯科技工士専門学校の講師をしており、技工士の先生とは近い関係にあります。 また、私が担当している教科は、被せ物や詰め物をつくる、歯冠修復技工学という学問なので、今回の問題とは一番直結している学問です。
今回の事件も、講義にて、話題としてお話していこうと思っております。
このように中国に発注するようになった背景は、技工料が安い、いうのが一番の理由だと思われます。
歯科業界が厳しいといわれる昨今、いかに経費を安くあげるか、というのが一つの課題かもしれません。
とはいえども、一般的な歯科医院、歯科技工所は、その状況下でも患者様にいい治療をめざして努力されています。厚労省が認めた金属しか使っていないという医院、技工所がほとんどだということをご理解いただければ幸いです。
心配な方は、かかりつけの先生に伺ってください。
= 補足 =
中国から日本に勉強にこられた歯科医師、技工士の方々にお会いする機会が今まで幾度となくありました。
彼らはみんな、まじめに歯科医療、歯科医学に取り組んでおられました。
中国の歯科医療、歯科技工物の全て問題があるわけではない、ということもご理解ください。
インプラントの使いまわしの問題について
2010年の1月、愛知県の歯科医院で、“使用済みのインプラントを他の患者に使いまわしをした疑いがある”、というニュースがありました。
当院はインプラント治療の患者様が多いこともあり、多くの方が話題にされました。
インプラント治療を行うにあたって、金属でできた人工の歯の根を顎の骨の中に埋め込む手術をする必要があります。(インプラントについて、詳しくは当ホームページのインプラントのコーナーを見てください。)
骨という本来なら手の触れないところを触るわけです。ですから、バイキンが入り、“感染”すれば、元も子もないわけです。
感染においては、神経質になってなりすぎることはありません。
例えば、インプラントを植えようと思い、お口の中にインプラントを入れたとしましょう。その時、偶然に患者さんがむせて、ツバがとインプラントの表面に付いたとしましょう。これで、そのインプラントはゴミ箱行きとなります。 インプラントの表面に、何か不純物やたんぱく質が付着するだけで使い物になりません。 ですから、“腫れものにさわる”くらいの慎重さが必要となります。
インプラントとはこのような感覚で行うため、使いまわしなんて考えられないことです。
どっかの喫茶店のランチでパセリが使いまわしされていた、という問題ではありません。
2010年の2月、偶然にもこの事件の直後に、日本口腔インプラント学会の支部学術大会が行われました。当院の歯科医師、岡崎正は、日本口腔インプラント学会の支部の元理事なので、当然学会には参加しました。やはり、学会でもこの話は取り沙汰されていました。
当院は、感染には最も注意を払い、手術用の滅菌した術衣を着て処置しております。服装だけではなく、全てにおいて感染がないように意識しております。 当院を始め、インプラントをまじめに取り組んでいる医院は使いまわしなどしておりませんので、ご安心ください。
= 補足 =
そのインプラント学会の時も、この事件に関しての詳細はまだつかめていないとのことでした。
http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY201001190505.html
朝日新聞のHPでこの記事がありましたが、読んでいて納得がいかないことが数点あります。
(引用)インプラント治療は、あごの骨に長さ2〜3センチの金属を埋め込んで人工の歯根を作り、その上に歯を作る。骨にしっかり結合させ、感染を防ぐ観点から、インプラントを扱う業者の添付文書では再使用や再滅菌を禁じている。
ここで、疑問になるのですが…
インプラントとは、上記に記したように、人工の歯根で、インプラント体自体は、骨に埋まってしまうわけです。
つまり、手元には残らず、“患者さんの口の中にある”わけです。
それを再利用するとはどういう意味でしょう?
インプラントのオペを行った、しかし、何かの不具合で脱落してしまった、という場合でしょうか。
インプラントが脱落するケースというのは、正直、ないわけではありません。が、非常にすくないケースであり、 “脱落したインプラント”が手元にたくさんあるとは考えられません。
また、この詳細は追っていきたいと思います。
Copyright c Okazaki Dental Office All Rights Reserved.